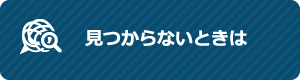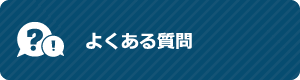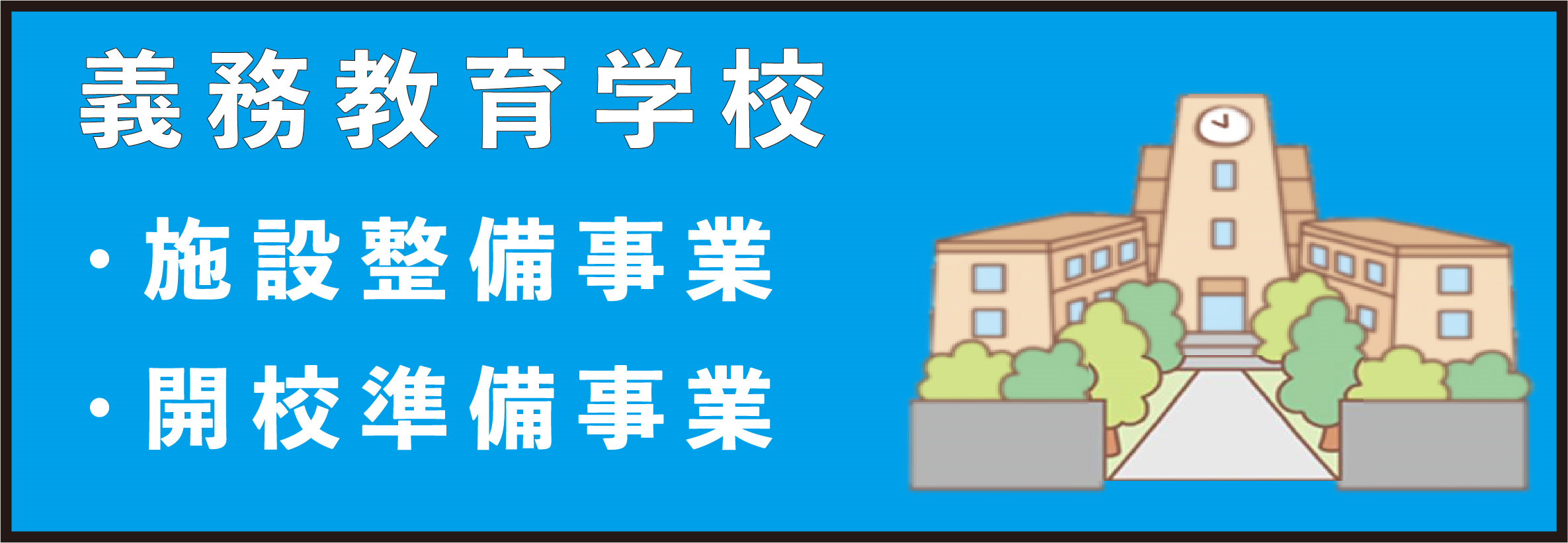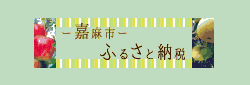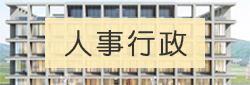本文
国民健康保険
目次
国民健康保険とは
国民健康保険(国保)とは、病気やけがをしたとき、安心して医療機関や薬局にかかれるように、被保険者(加入者)みんなが普段からお金を出し合い、医療費の負担を支えあう助け合いの制度です。原則として、すべての人が何らかの健康保険に加入することとされています。
国保にはこんな人が加入します
職場の健康保険(健康保険組合・共済組合・船員保険などの被保険者および被扶養者)、後期高齢者医療制度に加入している方や生活保護を受けている方以外、すべての人が国保に加入することになります。
- お店などを経営している自営業の人
- 農業を営んでいる人
- パート、アルバイトなどで職場の健康保険に加入していない人
- 退職して職場の健康保険などをやめた人とその被扶養者となっていた人など
国民健康保険の給付
国保に加入している方が病気やケガをしたとき、国保を取り扱う医療機関に国民健康保険証等を提出すれば、医療機関の窓口では医療費の一部を負担することで治療を受けることができます。
こんなときに受けられます。
- 診察
- レントゲン撮影、検査
- 病気やケガの治療
- 入院、看護の費用(食事代は別です)
- 治療に必要な薬や注射
出産育児一時金
国民健康保険の被保険者が出産したときに、世帯主に対して支給されます
被保険者が出産した場合、出産育児一時金が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。ただし、国保加入以前1年以上継続して会社等に勤務後、退職して6か月以内に出産した方は、国民健康保険からは支給されず、以前に加入していた健康保険からの支給となりますので、そちらにご確認下さい。
支給額
出生児1人につき48万8千円。ただし、産科医療補償制度(※1)の加算対象出産の場合は、50万円。
※1) 産科医療補償制度とは、平成21年1月1日以降に生まれた赤ちゃんを対象に、分娩に関連して重度の脳性麻痺を発症した場合、補償金が支給される制度です。分娩を取り扱っている病院、診療所、助産所が「財団法人日本医療機能評価機構」の運営する保険に加入することにより、補償が受けられます。
支払い方法
- 医療機関等への直接支払い(直接支払制度)
出産育児一時金の申請と受取を国保の加入者に代わって医療機関等が行うことにより、出産育児一時金が医療機関等に直接支給されます。 出産費用が出産育児一時金の支給額を超えた分は自己負担となり、下回った場合には、後日通知が届きますので、そちらをお持ちになって申請を行うことにより差額分が世帯主に支給されます。 - 出産後の申請に基づく支給
医療機関等への直接支払制度等の利用をしない(できない)場合や海外での出産、直接支払制度の利用後の差額がある場合の支給については、窓口での申請が必要ですので、窓口もしくはお電話でお尋ねください。
申請に必要なもの
- 出産等された方の保険証、資格確認書もしくは資格情報のお知らせ
- 母子手帳
- 印鑑(世帯主がお手続きされる場合は不要です。)
- 世帯主の通帳
- 本人確認できるもの(運転免許証等)
- 世帯主のマイナンバーが確認できるもの
直接支払制度等を利用しない場合は、これのほか「直接支払制度を利用しないことがわかる書類」、「出産等に伴う領収証」が必要となります。
葬祭費
国民健康保険の被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行った人(喪主等)に3万円支給されます。
申請に必要なもの
- 亡くなった方の保険証、資格確認書もしくは資格情報のお知らせ
- 会葬礼状など葬儀を行なったことが分かるもの
- 喪主等の印鑑(喪主等がお手続きされる場合は不要です。)
- 喪主等の通帳
- 本人確認できるもの(運転免許証等)
移送費
緊急でやむを得ず、医師の指示により移動が困難な重病人の転院などの移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合に支給されます。
申請に必要なもの
- 移送された方の保険証、資格確認書もしくは資格情報のお知らせ
- 医師の意見書
- 領収書
- 世帯主の印鑑(世帯主がお手続きされる場合は不要です。)
- 世帯主の通帳
- 本人確認できるもの(運転免許証等)
- 世帯主および移送された方のマイナンバーが確認できるもの
療養費
国民健康保険の加入者が、次のような場合には、治療等に要した費用を一旦全額自己負担となりますが、国保の窓口で申請をして、内容審査の上、認められると療養費として、医療機関等へ支払った費用の金額から負担割合に基づく自己負担相当額を除いた金額があとから払い戻されます。
| 一旦全額自己負担したとき(主なもの) | |
|---|---|
| 1 | 急病などでやむを得ず、国保を扱っていない医療機関にかかったり、保険証等を提示せずに治療を受けたりしたときなど(国民健康保険税の滞納により被保険者資格証明書等が交付されている場合を除きます。) 申請する際は、診療報酬明細書と下記のものが必要です。 |
| 2 | 治療用装具(コルセット、ギプス、義足など)を購入したとき※2) 申請する際は、医師の意見書(医証)及び装着証明書、見積書、請求書と下記のものが必要です。 |
| 3 | 輸血のための生血代(病院を通じて購入した場合)※2) 申請する際は、医師の診断書、輸血用生血受領証明書と下記のものが必要です |
※2)医師が認めた場合に適用されます。
なお、療養費は、治療等に要した費用を医療機関等へ支払った日の翌日から起算して2年が経過すると、時効となります。
申請に必要なもの
上表の書類のほかに、
- 療養費支給申請書
- 治療等を受けた方の保険証、資格確認書もしくは資格情報のお知らせ
- 領収書
- 世帯主の印鑑(世帯主が手続きされる場合は不要です。)
- 世帯主の通帳
- 本人確認できるもの(運転免許証等)
- 世帯主および治療等を受けた方のマイナンバーの確認できるもの
添付ファイル
国民健康保険に加入するとき
※国民健康保険に加入するとき、またはやめるときは、14日以内に届け出を行ってください。
手続きが遅れると次のようなことが起こります。
- 手続きした日より前の医療費について、国民健康保険の給付が認められない場合があります。(医療費を10割負担していただく場合があります)
- 保険税をさかのぼって一度に払わなければならなくなります。
| 加入の状況 | 手続きに必要なもの | |
|---|---|---|
| (1)他の市区町村から転入したとき |
転出証明書 |
・マイナンバーが確認できるもの ・本人確認できるもの(運転免許証等)
|
| (2)他の健康保険などを脱退したとき |
他の健康保険の資格喪失連絡票(資格喪失証明書) |
|
| (3)生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止決定通知書 |
|
| (4)子供が生まれたとき | 母子手帳 | |
| (5)外国人が加入するとき |
在留カードなど |
|
※別世帯の人が手続きするときは、委任状と委任された人の本人確認できるもの(運転免許証等)が必要です。
国民健康保険を脱退するとき
| 脱退の状況 | 手続きに必要なもの | |
|---|---|---|
| (1)他の市区町村に転出したとき | 保険証、資格確認書もしくは資格情報のお知らせ |
・マイナンバーが確認できるもの ・本人確認ができるもの(運転免許証等) |
| (2)他の健康保険などへ加入したとき | 国保の保険証、資格確認書もしくは資格情報のお知らせ | |
| 他の健康保険の保険証、資格確認書もしくは資格情報のお知らせ (国保を脱退する人全員分必要です) |
||
| (3)生活保護を受けることになったとき |
保護開始決定通知書 保険証、資格確認書もしくは資格情報のお知らせ |
|
| (4)死亡したとき | 保険証、資格確認書もしくは資格情報のお知らせ | |
| (5)外国人が脱退するとき |
在留カード等 保険証、資格確認書もしくは資格情報のお知らせ |
|
郵送による国民健康保険脱退の手続きについて
郵送手続きには以下の書類が必要となります。
※必要書類が不足している場合は受理できませんので、送付忘れのないようご注意をお願いします。
書類は下記郵送先へ郵送してください。
(1)顔写真付きの本人確認書類のコピー
(例)運転免許証等
(2)マイナンバーのわかる書類のコピー
(3)社会保険の資格確認書もしくは資格情報のお知らせのコピー(人数分)
(社会保険資格取得証明書のコピーでも可能です)
(4)国民健康保険の資格確認書もしくは資格情報のお知らせ(原本:ない場合は異動届の余白に紛失した旨をご記載ください)
(5)異動届 [PDFファイル/102KB](黄色部分に関して対象人数に応じて記載をしてください)
郵送先
〒820-0292
福岡県嘉麻市岩崎1180番地1
市民課 国保年金係
そのほか 変更の手続きが必要なもの
| その他の状況 | 手続きに必要なもの | |
|---|---|---|
| (1)住所、世帯主、氏名などが変わったとき | 保険証、資格確認書もしくは資格情報のお知らせ |
・マイナンバーが確認できるもの ・本人確認できるもの(運転免許証等) |
| (2)世帯分離や世帯合併をしたとき | 保険証、資格確認書もしくは資格情報のお知らせ | |
| (3)資格確認書等を紛失したり汚して使えないとき | ||
| (4)修学のため、子どもが他市区町村に住むとき |
在学証明書 保険証、資格確認書もしくは資格情報のお知らせ |
|
※別世帯の人が手続きするときは、委任状と委任された人の本人確認できるもの(運転免許証等)が必要です。
お問合せ・届出窓口
本庁舎 市民課 国保年金係 電話:0948-42-7426
山田総合支所 市民サービス課 市民サービス係 電話:0948-53-1119
碓井総合支所 市民サービス課 市民サービス係 電話:0948-62-5668
嘉穂総合支所 市民サービス課 市民サービス係 電話:0948-57-3187